| |
1999年、箕輪はジュビロ磐田に加入した。この年の新加入選手は、西紀寛と金沢浄(現FC東京)と箕輪の、わずか3名だけだった。
思いがけず、プロチームの最高峰でスタートを切ったとはいえ、それは苦悩の始まりだった。
「なんとかついていけるんじゃないかっていう軽い気持ちもあったんです。もう、とんでもない。本当に俺、生ぬるいところでやってたんだなぁって。毎日、苦しかったですね。すごいかけ離れているところでやっている人たちを必死で追いかけている感じだった」
周囲を見渡せば、確かな技術があり共通理解として戦術が完璧に浸透しているチームメイトたちがいる。突然、ぽんと放り込まれたプロの世界で、初めて味わう孤独の闇は深かった。
「パスを出しても『そこじゃない、こっちだろ』って言われる。技術、戦術からすべて言葉にできる人たちのなかに入っても、俺は、実践や感覚でしかやってこなかったから言葉にできなくて会話にならなかったんです。1年目の半分は…、いや、1年通してですね。恐かったです、ボールが来るのが。頭も追いつかないし体も追いつかない。『ボール来るな、パス来るな』っていつも思ってました」
自分らしさを失ってしまった箕輪は、毎週オフになると地元に向けて車を走らせた。必ず、高校のグラウンドに向かい後輩たちと汗を流した。習慣となったオフの過ごし方は、自分の成長を確認する貴重な場となった。そして、忘れてしまったサッカーの楽しさを思いおこさせてくれるなににも代えがたい時間でもあった。
|
|
|
|
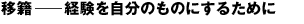
2年目に入ると、箕輪は長かったトンネルをふっと抜けた自分を感じられるようになった。
「紅白戦とかでプレーしても『お前が入ってもちゃんと11人になれるようになってきた』って言われて、それがすごいうれしかった。俺もやっと、チームの流れに乗れているんだなって」
1年目は、「11人で試合していてもお前ひとりだけ浮いている」と言われたほど周囲とギャップがあったことを思えば格段の進歩である。ジュビロ磐田の一員としてやっと認めてもらったような安堵感とともに沸きあがってきた「試合に出たい」という欲望を抑えることなどできなかった。
早速、行動に移した。当時のハジェヴスキー監督に、箕輪は「チャンスがほしい」と直訴する。だが、答えは「経験がないから使えない」というものだった。そのときアドバイスをされた課題を練習でクリアできたと思えた頃、再び監督のもとを訪ねた。だが、結局は「経験がない」ことを理由にチャンスは巡ってこなかった。「移籍」が脳裏をかすめた。
「俺も若かったから、監督にそう言われてキレてしまったところもあって…。出られないのに『経験』って言われてもどこで積めばいいんだよって。大卒でチームに入って、いくら磐田の看板背負ってても、このままではサッカー人生が終わってしまう。それで、チームに移籍先を探してもらったんです」
箕輪は、かつてのチームメイトであり尊敬する前田浩二に電話をかけた。前田は、何度か移籍を経験していた。
「前田さんは『逃げ道を作るようで俺はレンタル(期限つき移籍)は嫌いだし、相手チームに失礼だ。いつか帰れるんだっていう気持ちだと、そのチームを心から好きになれないんじゃないか』って話をしてくれて。最初は、すべて賛同するわけじゃなかったけど、考えていくうちに、ああ、確かにそうかもしれないって。影響を受けましたね」
 |
|
2000年9月、箕輪は地元川崎のプロチームに完全移籍をした。11月、セレッソ大阪戦で初出場を果たした箕輪は、PKを献上する苦い経験をしたことも含め、ピッチの感触と勝利の余韻に浸った。当時のインタビューで、「試合が終わったとき、磐田で積み重ねてきた1年半が思い起こされ、涙が出てきました」と答えている。
それから3年間、フロンターレでレギュラーとして定着し、欲しかった「経験」を手にいれた。
「2001年の頃は、このチームをあげるんだ!っていう勢いだけでやってました。途中で代えられてロッカールームの壁を蹴ったりしたこともあります。いまでは、考えられないですけど」と言って照れくさそうに3年前を振り返った。
「昔の意固地だった自分が、少し柔らかくなったのかもしれません。試合に出ていろんな人たちと組んでプレーをすることで、人の意見も聞けるようになったし、割り切って物事を考えられるようになった」
精神面の変化や積み重ねた経験は、プレーの幅につながった。感覚に頼るだけのかつての自分とは、もう決別した。
「選べるカードがすごい増えましたよね。石さんが監督をやっていたときにプレッシングサッカーとリアクションサッカーのふたつのサッカーを経験した。今年はそのふたつを組み合わせた感じだから、活かすことができるし、どうすべきかを言葉にもできるようになった。例えば、今年でいえば相馬さんの意見を聞きながら、自分のもつ選択肢のなかからプレーを選ぶ、という感じ。それが経験なのかな」
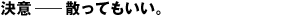
「俺は、あした散ってもいい。そのぐらいの気持ちでいきます」
昨年の終盤、残り3試合となった第42節の対福岡戦の前日に、箕輪は試合に賭ける想いを、そう話していた。あと1枚イエローカードをもらえば、2試合出場停止になる。その思いが、アウェイで洗礼を受けた甲府戦で、箕輪を無意識のうちに萎縮させていた。
「俺たちもいるじゃないですか。らしくないっすよ、ミノさん。俺もいつでも出られる準備しているから」
|
|

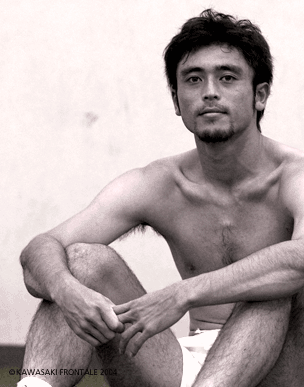 |
|
練習を終え、スパイクの紐を並んでほどいていたとき、岡山一成に声をかけられ、微かな迷いはふっきれた。
「確かに、自分でも最後まで試合に出たいっていう気持ちが心の奥にあったんです。同じ頃、ツトさん(高畠コーチ)にも『お前は自分のプレーを精一杯やれ』って言われたし、オカの言葉で思いっきりやろうって思えました」
決意と昇格を信じる気持ちは最後まで揺らがなかった。平塚戦が引き分けに終わっても変わることはなかった。
「だって、まだ全部が終わってなかったから。確かに引き分けたことはへこんだけど、自分たちがここまで追い込んだんだってしか思えなかったから」
結局、最後まで箕輪はピッチに立ち続けた。だが、勝ち点1が「このチームでJ1へ」という夢を阻んだ。
「泣いちゃいけないと思ってたんですけど…。どこを見ていいかわかんなかった。下見ちゃ情けないし、ファンを見ても悲しそうだし。焦点が合わない感じで、涙がぼろぼろ出てきた。泣いた理由は、こんなに楽しくサッカーをやったのに結果が出なかったということと、使い続けてくれた石さんに結果をお返しできなかったこと。それが一番悲しかったし情けなかった」
2004年3月。戦いのときは、再び幕を開ける。
生まれ育った土地にあるプロチームの一員である誇りが、箕輪を輝かせる。
「試合に出ていろんな状況でやって、昨年の最後とか、ああいう経験もして揺らがなくなった分、強くなれたと思うし、落ち着いてできるようになった。それが、今の強みかな」
|

仙台大学から1999年、ジュビロ磐田に加入。2000年秋に川崎フロンターレに移籍。
1976年6月2日生まれ、神奈川県川崎市出身。187cm、82kg。 |
 |
|
![]() 2004/vol.02
2004/vol.02



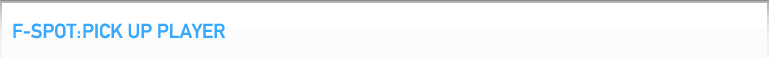
![]() 2004/vol.02
2004/vol.02



