| |
中学生になると、学校から帰り自転車で15分の距離にある横浜マリノス・ジュニアユースの練習に参加する毎日がはじまった。中学2年のときには、高円宮杯で全国優勝を果たしている。「僕たちの頃は、まだ県大会どまり。佐原の頃からすごい強くなったはずですよ」というのは、小学校4年から同じく日産FCプライマリーに入りジュニアユースに進んだ寺田周平だ。神奈川県の精鋭が集う集団へと進化している時期だった。桐光学園高校は、フロンターレの練習場と同じ川崎市麻生区にある。1978年にサッカー部が創設され、1986年に現在の佐熊裕和監督が就任し、スピーディーで構成力があるサッカーを展開し神奈川有数の強豪校として名を馳せてきた。あえて高校サッカーの道を選んだ佐原は、1年からレギュラーとして試合に出ている。

 4月のある日、桐光学園高校を訪ね、現在も指揮を執る佐熊監督に当時の佐原について話を聞いた。 4月のある日、桐光学園高校を訪ね、現在も指揮を執る佐熊監督に当時の佐原について話を聞いた。
「身長は、すでに今ぐらいありましたね。最初の印象は、ストロングポイントは身体ですよね。器用な選手ではなかった。2年の途中ぐらいまでは1対1とか筋力的にはそこまで強いという感じではなかったんで、よく我慢してやってました。3年になって、ある程度自信がついてプレーものびてきましたね。あの年は何人か人材もいたし、まじめな子もいたんですけど、試合経験も一番あったし(キャプテンは)佐原でやっていこうということになって。まぁ、あの性格ですからねぇ、キャプテンをやらせたのは賭けでした」(佐熊監督)
佐熊監督に話を聞きに行くことを事前に告げると、佐原の背筋は音が聞こえそうなほどにシャキッと伸びた。
「本当に俺はよく怒られていた。キャプテンは怒られ役なんだけど。俺よりしっかりしてる人もいたから、噂はあったけど本当にキャプテンになるかはわかんなかった」(佐原)
佐熊監督によると「キャプテンじゃなくても佐原は怒られてたと思いますよ(笑)」という。「まぁでも、(キャプテンになったことが)うまい方にでましたよね。思い出深いことですか? 12月に選手権の調整合宿を張ったときのことですかね。コテージになっていて、ある時、コテージごとにオレンジジュースを取りに来なさいと選手たちに伝えたときに、ひとり1年生がなんの断りなしにもっていこうとして『お前は帰れ!』って帰そうとしたんです。そしたら佐原が、その1年生と一緒に謝りにきた。成長したなぁと印象に残ってます。下級生の面倒はけっこうみてましたね」
佐原キャプテン率いる桐光学園高校は、確かな技術とパスをつなぐサッカーで注目を集め、選手権決勝まで進んだ。大会期間中に風邪で体調を崩す選手が多いなかで戦った決勝戦は、北嶋(清水エスパルス)がいる市立船橋と対戦し1対2で敗れた。当時、佐原の同級生に、同じくマリノスジュニアユースから桐光学園へと歩んだ中村俊輔がいたのは周知の事実だろう。
「決勝に負けてみんな泣いてたけど俺は泣かなかった。みんな負けてガクッと落ちてたから、監督に『お前がしっかりやらせろ』って言われて、挨拶とか最後までみんなにやらせたことは覚えてる。高校サッカーは選手権っていう目標があるから楽しかった。選手権に2回、インターハイにも2回出られたしね」
|
|


|
|
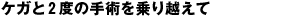
1997年、フロンターレが新しい一歩を踏み始めたと同時に加入した佐原は1年間のグレミオ留学に旅立つ。寮生活を送りながらジュニオールの練習に参加し、帰国前にはコパ・サンパウロに出場を果たした。
「最初は、きつかった。言葉も生活も練習も。日本人だから下手だと思われてたし紅白戦とかにも出られなかったからね。でも、徐々に認めてもらえるようになって練習試合とかに出るようになって、最後は大会に出してもらった。ブラジルのサッカーは当たりが強くて、みんな気持ちがすごいハングリーだった」
1999年には、佐原は中西哲生、森川拓巳と3バックの一角を担い、チームのJ1昇格に貢献。翌2000年、選手が大幅に補強されてもなお、開幕スタメンに名を連ねていたのだが…。
それは、突然の出来事だった。練習での紅白戦で、左ヒザを捻って着地し半月版を損傷してしまう。結局、その年のほとんどをリハビリに費やし、2001年のキャンプに照準を合わせていたが、キャンプ初日に再びヒザに違和感を覚え、治療を試みたが痛みがとれず、2回目の手術に踏み切った。
「まじ、きつかった。落ち込んだね。しょうがないなって開き直ってはいたけど…。あの頃、周平さんもいたからふたりでリハビリだったなぁ」
あまり緊張することはない、という佐原も、2年ぶりの試合は「ジェットコースターから降りるような気分」だったという。2002年3月21日、J2第4節対セレッソ戦のことである。結果は2対2のドローだった。
「寝れないとかはなかったけど、ほんっと久しぶりだったからね。慣れるまでちょっと時間がかかった。練習試合とは、プレッシャーが全然違うし」
2002年はリーグ戦に13試合出場したが、昨年はチームが昇格争いをするなか1試合もベンチにすら入ることはなく最終戦を迎えた。
──昨年の最終戦で、泣いていたけど?
「あれは、もらい泣きした」
──なぜ?
「みんな泣いてたから。選手もそうだし、サポーターがみんな泣いてて…。だけど俺、なにも今年やってねぇなぁって思って、自分に対してちょっと悔しいっていうのもあった。出られない悔しさはあったけど、チームには上がってほしいと思ってたから、複雑だよね。調子は悪くなかったよ。20歳ぐらいなら腐ってたと思うけど、自分より若いやつらもいるしね。その辺はおとなになった」
 |
|

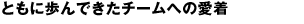 プロ選手は、試合に出て成長を遂げることはいうまでもない。そこで得られる経験や実践を積むことで技術的にも精神面においても成熟していく。そして、試合に出る権利を勝ちとるために練習において自分自身を鍛錬し、アピールすることは不可欠だ。さらにいえば、高畠コーチの言葉を借りれば「評価は自分でするものではなく他人がすること」だということも、当たり前のようだが厳しさにつながる。 プロ選手は、試合に出て成長を遂げることはいうまでもない。そこで得られる経験や実践を積むことで技術的にも精神面においても成熟していく。そして、試合に出る権利を勝ちとるために練習において自分自身を鍛錬し、アピールすることは不可欠だ。さらにいえば、高畠コーチの言葉を借りれば「評価は自分でするものではなく他人がすること」だということも、当たり前のようだが厳しさにつながる。
競争社会のジレンマは誰もが経験することだろう。常に常勝チームで勝つ喜びを味わってきた佐原は、フロンターレに加入してからも、わずか3年目でレギュラーとして昇格の喜びを味わった。だが、その後ケガで約2年間を棒に振り、昨年も試合に出られない悔しさを経験した彼にとって、今年は間違いなく新たなチャレンジとなる年だ。
「監督にも選手たちに競わせるということを言われているから頑張りたいし、やっぱり試合に出たい。チャンスがきたら結果を出したいし、出た試合は勝ちたい。もう今年こそ、チームとしてJ1に上がらなきゃいけないしね。チームが勝ってそのなかで自分が少しでも貢献できたら…。このチームに愛着あるしね。移籍をしたり環境を変えたりっていうのも選手にとってはあるかもしれないけど、ずっと同じチームでやれることほど嬉しいことはないと俺は思ってるから」
5月15日、第12節対水戸戦で久しぶりに帯同した佐原はベンチに入らない17人目のメンバーとして、競技場にいた。「点、取って来いよ!」とチームメイトに檄を飛ばして──。
この日、26回目の誕生日を迎えた。 |
|

 |
|
|
 |
|

1997年、桐光学園高校より川崎フロンターレに加入し、1年間のグレミオ留学を経験する。今年8年目となるフロンターレ生え抜き選手。1978年5月15日生まれ、神奈川県出身。184cm、75kg。 |
|
![]() 2004/vol.04
2004/vol.04
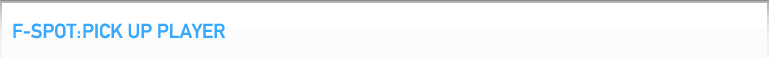
![]() 2004/vol.04
2004/vol.04
